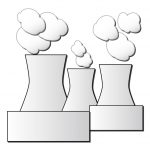高齢化社会で、その上に少子化が進んでいる日本の社会では労働人口は少なくなっていく一方となってきています。
この状態をそのまま放って置いてしまうと経営が立ち行かなくなる会社が多くなっていくことが予想されるのです。
そこで日本の政府はキャッチフレーズとして一億総活躍社会というものを掲げ高齢者を活用したり、女性を社会に進出させたり、個人の需要に応じた働き方を提案して実現させようとしています。
この日本政府が行っている施策のことを働き方改革と言い、それに伴って制定されたのが働き方改革関連法です。
生活に占める労働時間のバランスを改めて見直して、健康で生産性が高い仕事をすることが目的になります。
働き方改革関連法は、ただ単純に制度化されただけではなく法的な効力があるのです。
例を挙げると残業する時間に上限を設定して、それ以上残業すると罰則が適用されます。
これは、いつの間にか慣習化していた残業や長時間労働を防止することが目的です。
会社にとって労働人口が少なくなることが原因の労働力不足が、深刻な課題となっています。
結果的に、経営に良くない影響を及ぼす会社も登場し始めました。
労働力が足りなくなるので事業やサービスの質が下がったり、営業時間を短くせざるを得なくなったり、事業を縮小する必要が生じたりなどといった影響を及ぼしているのです。
その上に人材を確保するために今まで以上に人件費が必要となり、経済的な負担が多くなることも課題になっています。
こういった問題を抱えている今だからこそ、これまでの日本の会社で働いていた方法が見直されているのです。
慣習化してしまった残業や長時間労働などを少なく抑えて、働く方法を見直すことによって高い生産性を得ることが目的になります。
働き方改革関連法案は、勤務間インターバル制度を促進することや残業時間の罰則付上限規制など幾つかの項目を中心にした改革です。
政府にとっても、働き方改革はメリットを得られます。
国民が快適に働くことが可能になることが目的ですが、そのことによって労働人口が多くなり税収が確保され、66歳以上の方を労働者として活用することが可能になれば、政府が支出する年金の金額が少なくなるなど財政的に良い方向に進んでいく訳です。
政府の働き方改革による取り組みは、同一労働同一賃金の実現と裁量労働制が適用される範囲を拡大することになります。
そして生活における労働時間が占める比率を低く抑えるという意味合いでも残業する時間に上限を設定して、働く人の健康状態を守ることに繋がる訳です。
働き方改革は労働時間を是正し、正規雇用と非正規雇用との間の賃金の格差を解消し、高齢者が働くことを促進することが挙げられます。
正規雇用と非正規雇用との間の賃金の格差を解消するためには、原則として同一の労働に同一の賃金を支払うという賃金制度に公平化することで非正規雇用労働者のモチベーションを高めて、生産性を高めることが期待可能です。
ところが会社が払う人件費が大幅に多くなることを考慮すると、なかなか簡単に実行出来るような施策ではありません。
高齢者が働くことを促進することは、今までに培ってきた経験を活用して若者に技術を伝承することが出来ます。
仕事場によっては、若い世代の労働者よりも能力を出せる場合も期待可能です。
働き方改革を実施することによって、労働時間が短くなり労働者の集中力や生産性も高くなることが期待出来ます。
従来のように時間がかかって、だらけた雰囲気を刷新することが可能です。
そして人材採用でも、働き方改革に力を入れている会社という社会的に良い評価が得られるというメリットがあります。
中でも若い世代は自分の生活スタイルを守りたいという気持ちが強いため、労働者を大事にする会社は注目されやすいです。
最終更新日 2025年12月25日 by donkor